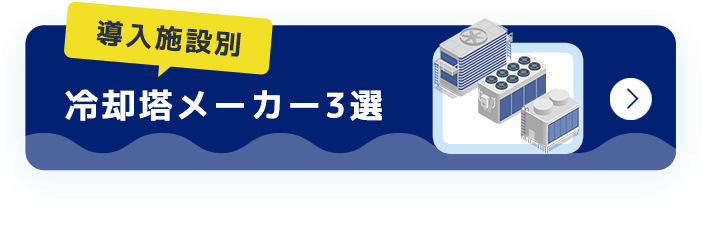冷却塔のファン(送風機)
冷却塔は、空調設備や産業プロセスで使用される冷却水を効率よく冷やす装置です。その中心的な役割を担うのがファン(送風機)であり、外気を取り込んで水と接触させることで、一部の水を蒸発させながら熱を奪う仕組みを可能にしています。今回は、ファンの概要や制御の必要性、故障の原因、そして故障時の対策などについて詳しく述べたうえで、ファンを用いないエゼクタ式冷却塔という方式も紹介します。
冷却塔のファン(送風機)とは
ファン(送風機)の種類
冷却塔のファンは、大きく分けて「軸流ファン」と「遠心ファン」の2種類が用いられています。
軸流ファン(プロペラファン)
その名のとおり、モーターの軸方向に風を送り出すタイプで、冷却塔内部に大量の空気を取り込むのに適した構造です。羽根がプロペラのように取り付けられ、比較的低い静圧でありながら大きな風量を得ることができるため、多くの冷却塔で一般的に使われています。
遠心ファン(シロッコファン)
回転軸と直角に空気の流れを変化させる仕組みで、一部の冷却塔や特殊な設計で採用されますが、軸流ファンほど一般的ではありません。
ファン(送風機)の
駆動方式
代表的なものでは「Vベルト駆動」「直結型駆動」「ギヤ駆動」の3種類が挙げられます。
Vベルト駆動
モーターとファンの間をVベルトでつないで回転数を調整します。構造がシンプルで部品も入手しやすい利点があるものの、ベルトの張り具合や摩耗など定期的な点検が欠かせません。
直結型駆動
モーターのシャフトに直接ファンを取り付ける方式で、小型の冷却塔によく採用されます。減速機構が不要であるため伝達ロスが少なく、メンテナンスも比較的容易ですが、大型化には向きにくい場合があります。
ギヤ駆動
モーターの回転を歯車(ギヤ)で減速してファンに伝える仕組みで、効率的に大きなトルクを得られる一方、ギヤ部へのオイル管理が必要となり、起動時にギヤ特有の衝撃音を伴うことがあります。
いずれの方式であっても、ファンが正常に作動していることは、冷却塔が想定どおりの性能を発揮するうえで不可欠です。冷却塔で効率よく水を冷やすためには、外気を十分な量取り込み、水との接触面を確保する必要があります。もしファンの風量が不足すれば、水が十分に冷えずに装置全体の効率が下がり、設備の能力不足を招きかねません。反対に過剰な風量を与えれば、不要な電力を浪費してしまいます。適切な風量バランスを保ち、安定運転を続けるために、ファンの状態をしっかりと把握することが重要と言えるでしょう。
ファン(送風機)での
制御が必要な理由
冷却塔にとって、ファンの制御は水温管理と省エネルギーの両面で欠かせない要素です。冷却水は季節や天候、あるいは使用環境の負荷変動によって必要な冷却量が変化します。たとえば真夏の炎天下であれば、冷却水の温度をしっかり下げなければならないためファンをフル回転させる必要がありますが、気温が低い時期や夜間などではそれほど強い風量は要らない場合が多くなります。
もしファンを常に全開運転のまま放置すると、必要以上に冷却水が冷えすぎることがあります。冷えすぎた水は設備によっては凍結を引き起こす可能性があり、その分エネルギーを無駄に消費してしまいます。一方で、必要な時に十分な風量を供給できないと、冷却能力が不足して設備の動作に支障が生じるかもしれません。
そこで、冷却塔のファンは適切な制御を行い、水温が一定範囲に収まるように管理する必要があります。方法としては大きく「ON-OFF運転」と「インバーターによる回転数制御」が挙げられます。
ON-OFF運転
もっとも簡単な制御方法で、水温が設定した上限を超えたらファンを稼働させ、下限に達したら停止する仕組みです。ただし短いサイクルで繰り返しON-OFFを行うと、モーターやベアリングに大きな負荷がかかり、故障リスクが高まるという課題があります。
インバーター制御
ファンの回転速度を細かく調整できるため、無駄のない運転を実現できます。回転数を段階的に落としたり上げたりして水温を安定させられるので、必要な風量をきめ細かく供給可能。その結果、省エネルギーとともに機器を長持ちさせる効果も期待できるでしょう。とはいえ、インバーター運転では一定の周波数帯で振動や騒音が発生することがあり、対策として共振帯を回避するジャンプ機能を活用するなどの配慮も必要です。
冷却塔のファン(送風機)が故障する原因
ファンの故障は冷却能力の低下や運転停止につながりかねないため、原因を理解して未然に防ぐことが重要です。代表的な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
モーターの劣化や故障
ファンを回転させるモーターは、長期の稼働によって内部ベアリングが摩耗するほか、電気的な不具合が生じる場合があります。一般的にベアリングの寿命は2~3年、モーター自体の耐用年数は7年前後とされますが、使用環境によって大きく異なります。異音や過熱、振動などが増えたら要注意です。
軸受(ベアリング)の損傷
ファンブレードが滑らかに回転するためには、軸受の健全性が欠かせません。摩耗が進むと羽根がスムーズに回らなくなり、異音や振動が大きくなります。最終的には回転が困難になることもあるため、軸受は定期的に注油や点検を行いましょう。
ベルトの緩みや切断
Vベルト駆動方式を採用している冷却塔では、ベルトの張り具合が重要です。長期間の使用でベルトが伸びたりひび割れを起こしたりすると、スリップによってファンの回転数が低下し、やがて切断に至ることがあります。ベルトの劣化を見過ごすと突然の停止を招くため、1年を目安に取り替えを検討してみてください。
ファンブレードの破損
羽根自体が経年劣化や衝撃、異物の混入などによって欠けることがあり、これも大きな振動や騒音の原因となります。ブレードの破損はファン全体のバランスを崩し、モーターや軸受に負担をかけるので早めに対処しましょう。
異物の混入
冷却塔内部には様々なゴミや落ち葉などが入りこむ可能性があります。大きな異物がファンの羽根に挟まれば、回転を阻害して故障に直結します。フィルターやスクリーンで異物をできるだけ防ぎつつ、定期点検時には冷却塔内部を清掃してトラブルを防ぐことが肝心です。
電気系統の異常
配線の断線やモーターへの過電流・過負荷など、電気的なトラブルも無視できません。制御盤の劣化や接点不良も含め、ファンが急に止まった際は電気系統の点検を最優先で行うと良いでしょう。
これらの原因は複合的に絡む場合も多く、単なるモーターの不調が引き金となってベルトやブレードにも悪影響が及ぶことがあります。早めに異常を検知して対処するためには、日常的な点検と定期メンテナンスが不可欠です。
ファン(送風機)の故障によって
冷却能力が低下した時の対策
ファンの故障が発生すると、冷却塔の性能が著しく落ち、設備全体の稼働に支障をきたす恐れがあります。そこで、故障を迅速に見つけ対策を講じることは非常に大切です。以下に代表的な対策を挙げます。
故障の兆候の早期発見
運転中に普段とは異なる異音や振動を感じたら、まずはファンの状態を疑って点検を行いましょう。音や振動はトラブルの前兆であることが多く、早期に原因を特定して部品の交換や修理を実施すれば、大事に至る前にトラブルを食い止められます。
定期的なメンテナンスと
部品交換
ベアリングやベルトなど、摩耗が進む部品はあらかじめ寿命を見越して計画的に交換することが大切です。Vベルトであれば1~2年、モーターのベアリングは2~3年、ファンブレードや翼車は5~7年を目安に劣化状況を確認し、早めの交換を検討してください。定期的にチェックしておけば、突然の停止を回避できるでしょう。
ファン制御による負荷軽減
インバーター制御を導入するなどして回転数を適切に抑えられれば、ファンへかかる負荷を軽くし、無理のない運転が継続できます。特に風量が余剰となる状況を回避することで、余分なエネルギー消費を防ぎながら、ファンやモーターを長持ちさせることができます。
専門業者への相談
故障や不具合が深刻化する前に、専門の業者へ相談するのも一つの手段です。ファンの摩耗状況、振動の程度、モーター内部の状態など、経験豊富な技術者ならではの視点で適切な修理や改善提案が得られます。自己判断でかえってトラブルが拡大する可能性もあるため、知識と実績のある業者に任せることが安全策と言えるでしょう。
故障によって生じる冷却能力の低下を長引かせないためには、異常の早期発見と未然防止が重要です。定期的な点検・メンテナンスを実施し、ファンが健全に動作しているかを常に把握する習慣が、安定稼働と設備の保護につながります。
ファンの無い冷却塔
(エゼクタ式)
冷却塔と聞くと、多くの人が大きなファンを想像するかもしれません。しかし、実はファンを使用しない冷却塔の方式も存在します。その代表的な例が「エゼクタ式冷却塔」です。エゼクタ(噴射器)の原理を利用することで、高温の流体のエネルギーを低温の流体に移動させ、蒸発・凝縮を繰り返して冷却を行います。高温側の熱エネルギーが作りだす蒸気の流れが、低温側の流体を吸引しながら圧縮して熱交換を進めるイメージです。
エゼクタ式冷却塔の
メリット
ファンがないため大きな送風機モーターが不要で、外部電力の削減効果が大いに期待できます。加えて、回転部がない分 機械的トラブルも減り、メンテナンスの手間を省ける利点があります。また、コンパクトな設置が可能で、ファンを設置するスペースが不要なため、省スペース化につながる点もメリットと言えるでしょう。
エゼクタ式冷却塔の
デメリット
ただし、エゼクタ式冷却塔を導入するには専門的な設計と運用管理が求められます。噴射器や配管の構成によっては十分に水が冷えない可能性もあり、設置環境や必要とされる冷却能力を慎重に考慮しなければなりません。運転条件を誤ると十分に熱が移動しないこともあり、適切なシミュレーションや試験運転を行う必要があります。加えて、エゼクタ式の効率は外気条件や処理する熱量との相性に左右されやすい面があるため、すべての場面に万能というわけではありません。
ファンを用いる通常の冷却塔では騒音や電力消費、故障リスクがある一方、エゼクタ式や自然通風式の冷却塔ではファンが不要になり、騒音の抑制や省エネルギーを大きく期待できます。近年は環境負荷を減らす取り組みや省エネ対策の高まりに伴って、エゼクタ式のような新技術にも注目が集まっていますが、実際に導入するかどうかは現場の条件やコストメリットを総合的に判断して決める必要があるでしょう。場合によっては専門家のアドバイスを仰ぎ、最も適切な冷却方式を選択することが望ましいと言えます。
冷却塔のファン(送風機)についてまとめ
故障を引き起こしやすい部分を理解し、早期発見・早期対処を心がけることで、長期にわたる安定稼働を実現できるでしょう。また、ファンを一切使わないエゼクタ式冷却塔や自然通風式冷却塔といった選択肢も存在し、環境や用途に応じて最適な方式を検討することが大切です。冷却塔の運用を見直し、トラブルを防ぎながら効率を最大化することが、経済的にも環境面でも大きなメリットにつながります。